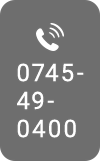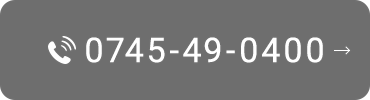もしかして適応障害?心や行動に現れる症状
 適応障害による症状は心理面や身体面に現れ、普段とは異なる行動が見られることがあります。
適応障害による症状は心理面や身体面に現れ、普段とは異なる行動が見られることがあります。
原因であるストレスが取り除かれると、これらの症状は通常、改善へと向かいます。
しかし、ストレスが継続し症状が改善されない場合は、うつ病や不安障害など、他の精神疾患へと移行するリスクも指摘されています。
心理的な症状
- 抑うつ
- 不安
- 焦り
- イライラ
- 悲壮感
- 無気力
- 思考力や集中力の低下
- 緊張
- 混乱
身体的な症状
- 頭痛
- 肩こり
- 腹痛
- 不眠
- 全身のだるさ
- 動悸
- 過呼吸
- 食欲不振
- 勝手に涙が出る
- 発汗
- めまい
- 手の震え
行動的な症状
- 不登校
- 無断欠勤
- 遅刻
- 早退
- 仕事のパフォーマンスの低下
- ひきこもり
- 過剰飲酒
- 暴飲暴食
適応障害とは
適応障害は、ストレスが原因で起こる心理的、身体的な不調です。
ストレス源がなくなれば速やかな改善が見込めます。
しかし、ストレスが持続すると、適応障害も通常続きます。
統合失調症や気分障害など他の精神疾患がある場合は、適応障害とは診断されません。
セルフチェック
「自分は適応障害かもしれない」と感じている方は、以下のチェック項目で症状を確認し、受診の目安にしてください。
- 憂うつな気持ちが続く
- 直近2週間で体重に2kg以上の増減があった
- 食欲がない
- 食事の味を感じない
- 何事にも興味が沸かない
- 自分はダメだと思ってしまう
- 死にたいと考えてしまう
- 不安を感じることが多い
- 常に何かに緊張しており落ち着かない
- 勝手に涙が流れる
- しっかりと休んでいるのに疲れやすく体がだるい
- めまいや立ちくらみ、吐き気などの症状がある
適応障害の原因・なりやすい人
適応障害の原因は、仕事のストレスや家庭問題、学校や恋愛の悩み、病気など生活全般にわたります。
どんな人がなりやすい?
 真面目で責任感が強い人は特に、適応障害になりやすい傾向があります。
真面目で責任感が強い人は特に、適応障害になりやすい傾向があります。
どんな方でも、ストレスの程度や種類により発症することがあり、ストレス管理が重要です。
適応障害の診断
診断においては、DSM-5やICD-11の基準に基づき、ストレス因の存在、症状の程度、社会生活への影響などが総合的に評価されます。
DSM-5による診断基準
- 「ストレス源に対して不釣り合いなほどの強い苦痛」または、「社会的、職業的、または他の重要な活動領域での顕著な機能障害」の少なくとも一つを満たし、証拠がある
- 他の精神疾患の基準を満たさない
- 正常な死別反応でない
- ストレス原因がなくなれば6ヶ月以内に症状が消失する
診断書の作成について
休職や職場環境の調整が必要と判断された場合、診断書の発行が可能です。適宜ご相談ください。
適応障害の治療
ストレス因子の除去
適応障害の症状は、ストレス源がなくなることで速やかに改善することが多いです。
「環境(ストレス源)に適応できるようにする」もしくは「ストレス源から離れる」ことが回復に向けた基本的なアプローチとなります。
薬物療法
適応障害の治療において、特定の薬がその原因を直接改善するわけではありません。
主に症状を和らげるための対症療法や心理療法が中心です。
補助的な治療手段として薬物療法がありますが、これは症状に応じたものです。
抗うつ薬
気分の落ち込みや意欲の低下の改善に使用します。
気分の落ち込みが特にひどい場合に処方されます。
抗不安薬
不安や緊張状態を抑える薬です。
特に不安感や焦り、興奮が強い場合に効果を発揮します。
睡眠薬
不眠症状が見られる場合に使用し、生活リズムを整えるのに役立ちます。
不眠は思考の整理を困難にしたり、不安やイライラを増大させたりする原因となるため、早期の管理が重要です。
認知行動療法
認知行動療法は、適応障害を持つ人が健康的な思考や行動パターンを身につけるのを助ける治療法です。
このアプローチは
- 誤った思考や認知の歪みを正し、現実に即した健全な認知へと変化させる
- 問題解決能力や環境への適応力を高める
- 不適切な行動を改善する
- 自尊心を向上させる
ことにも焦点を当てています。
最終的には、適応障害の再発を防ぐためのスキルをご本人に身につけていただくことが目標です。
周りの人が適応障害になった時の接し方は?
過干渉しない
適応障害に罹患している人に対しては、心配しすぎず、必要以上に干渉しないようにします。
過度な関与は相手を疲れさせる場合や負担を増やす場合があります。
否定しない
相手の話を聞く際には、否定せず、ゆっくりと耳を傾けることが大切です。
相手の言葉を受け入れ、共感することで、安心感を与えることができます。
強要しない
無理強いは本人に負担をかける可能性があります。
まずはゆっくりと休息を取り、余裕が出てきてから徐々に提案をしていくことが重要です。